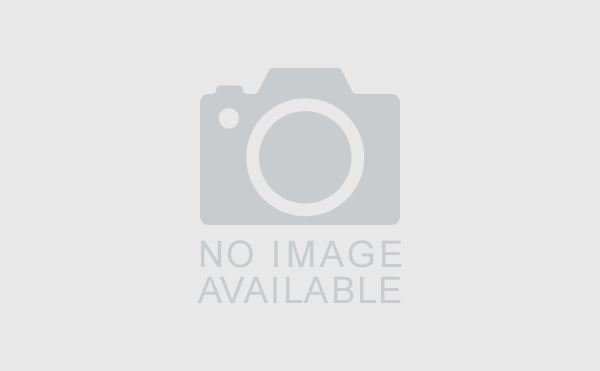若かりしショパンの肖像画のある本②
このクレチインスキーの書籍は、
内容量としてはそれほど多くはない。
この英訳者のナタリー・ヤノタ嬢は
当時のショパン音楽院の教授をしていたユリウス・ヤノタ氏のお嬢さん。
パデレフスキーに匹敵するほど人気があるピアニストだったようで
パデレフスキ―は彼女に曲を献呈しているらしい。
いろんな師についたようで、クララ・シューマンやブラームスの名もある。
当時としては初めての男性ズボンを履いた、女流登山家としても有名であったことは、
彼女の特徴的なエピソード。
一般女子とはかなり違っていたようである。
「弟子から見たショパン」の本の説明では、
ショパンの姉が、一度チャルトルィスカ侯爵婦人にショパンの草稿を渡し、
それが回ってナタリー・ヤノタ嬢に遺贈されており、
その一部が彼女の訳したこのクレチインスキーの英訳本の一部に載っていると
紹介されているのだけれど
3人の女性の間にかなりの信頼関係を想像させられる。
クレチインスキーのこの本には、かなり私情が盛り込まれており
エンゲルティンゲル氏の解説によれば、いい加減な抜粋と加筆があるということらしいが、
ショパンのお気に入り女性弟子の筆頭であったチャルトルィスカ婦人からも彼は教えを受け、
ショパンの演奏がどんなものであったかを受け継いだともある…。
彼はショパン音楽院の教鞭も執っていたとあるし、
ワルシャワでショパンの講演をした記録もあることから、
ショパンに対する敬愛の念の深さは、
同じくショパンに関して遺した書籍や講演の多く、またショパンの弟子ではなかった二―クスと
並ぶ感触を受ける。
印象的だったクレチインスキの文言としては、
「皆、ショパンを重く弾きすぎる、ショパンはもっと軽い手で弾くべきだ」というもの。
ショパンのタッチに関しては、
人によっていかようにも解釈することになるだろうから、
軽いという意味が何を指しているのか深堀りしなければ真相は見えてこない気がする。
そんなことから
私が興味があるのは、楽曲分析はさておき
ショパンが打鍵にどんな神経回路を使っていたかという側面。
楽曲分析ができても、
ショパンがそこに要求したその音を再現するスキル、
つまりそれを音として実現し変化できる技術の存在を無視してしまうと、
その意味は生かし切れなくなる..と考える。
「弟子からみたショパン」の中にある、音楽会を描いたデッサン画を見ると、
鑑賞する人によって感じ方は違うだろうけれど、
私にはショパンの中にある感情が、よく表現された姿勢、表情に見えるような気がする。
弟子ではなかったクレチインスキーのショパン分析には
ショパンの女性筆頭弟子の公爵夫人から伝わったものが、大きくあるということが
この書籍の真相のようだ。
クレチインスキーが遺した少ない書籍の中の一つではあるけれど、
鍵盤の扱いに関する箇所に際して、
意味不明…(-_-;)というものは無かったと振り返る。
「弟子から見たショパン」のエンゲル氏の意見によれば、
ショパンの指の形についてのクレチインスキーの証言は
何かの間違いだろうと指摘されているけれど
私には、
一概にそうとは言い切れない微妙なものがある気がしてならない。
この本は確かに、表記ミスや番号ミスが多々あったりして、
編集としては、やや雑さを感じるものだけれども
イギリスの前所有者のメモ書きやサインがはっきりと残っているのを見ると
1900年代初頭から英語圏を旅し、はるばるここへ来てくれた長い軌跡として、
なんとも感慨深い…