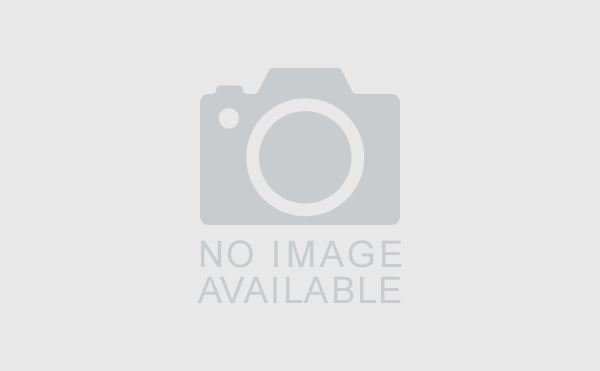みっちりな一日。
古楽器と現代楽器の魅力をお届けする主旨で、
フラウト・トラヴェルソとクリストフォリ・フォルテピアノ、
現代フルートと現代ピアノ(会場の楽器は、少々古いフルコンのヤマハ)が
プログラムするコンサートを、先日終えた。
私は、現代ピアノの担当で、
古楽器の詳しい勉強を専門的にしてきた共演者からすると、
ほぼ知識ゼロの輩だったが、
僭越ながら古楽器から発展してきた現代ピアノへの<繋がり>を
紹介する役目となった。
材料や機能の歴史とその内容をショートストーリーでお届けしたく準備したのだが、
ピアノアクションなど、とにかく内部に隠れた部分に特徴があるゆえ、
なかなか表現が難しかった。
時間的にはわずか10分余り程度のトークで、
もっと自分でも話しやすくできたはずだが、粋なセリフの面白い脚本も作れず、
そもそも普段のコンサートのMCすら苦手な自分のカミカミも重なって、
複雑なものを明瞭に、というよりも
マニアっぽい印象を持たせてしまったかも(-_-;)と反省である。
時代は遡り、基本の古楽器の説明は、
専門の共演者さんたちからしっかりあったので
内容も多く、時間ギリギリでパッツパツの進行であったが、
フラウト・トラヴェルソの気品溢れた世界や、
持込したクリストフォリ・フォルテピアノの音色も
あまり聴く機会の少ない楽器という面では、
お客様に楽しんで頂けたのではないかと感じている。
自主開催ゆえ、会場設営もホールスタッフの方の誘導に従って、
自分ですることが必須だったので、
リハ前に、椅子出しやら反響板設置やら、力を要するミッションがあったことは、
正直大変だったけれど、
人を雇うほど、経費は見込めなかったのでいたしかたない。
ホールスタッフさんのご提案で、
備品椅子でなく、希望席数に合わせてパイプ椅子を並べ直すことにしたが、
少人数の席数の場合、
椅子と椅子を詰めず、空間に余裕を取ることができ、
つまり隣の人と少し距離を取ることができるので、
お客様のお耳にとっては、その方が良い環境になるのでは、
と感じたりした。
ショパンが残したとされる
「彼は何千人もの人に聴かせるように弾くが、
私はただ一人の人に聴かせるために弾く」という言葉。
いかに音の質を大切に想い、聴衆に届けたいと思っていたか。
私は、いつも忘れてはならない大切なことと感じていたが、
今回のコンサートでは、内容に通じて、一層深く感じるものとなった。
貴族的なサロンスタイルで
弾いて、聴いて、お互いに奏者の音を楽しんだ古楽器からショパンの時代を経て、
現代の大ホールコンサートまで進化してきた歴史は長いが
最近は、その上にさまざまなスタイルの演奏会が見られるようにもなった。
視覚効果も要求されるのか...
演奏終わりにフォトタイムが設けられているものも出現。
私が留学する前は、
コンサート中に演奏者が舞台上で声を発することすら珍しかった記憶だが
こうした昔のクラシックコンサート形式は、
もう物足りないと言われていくのであろうか...
プログラム構成を含め、
何かしらの工夫や考案は、常に必要であり必須であるけれど、
エンターテイメントの認識が変わりつつある今日この頃においては
内容ですべてを賄おうとすると、
需要と供給が一致しなくなる現実があることは、
正直、昔の私が全く想像しなかった、大きな戸惑いである。
が、
かつての時代に生きた作曲者への敬意を忘れず、
決して多人数ではない聴衆であっても、
それぞれ有意義な時間に感じていただけるようなものを
提供できる演者でありたいベースは、やはり今も変わらない。
そして名古屋市から外れた郊外にも関わらず、
足をお運びくださったお客様とお天気に、感謝ばかりである