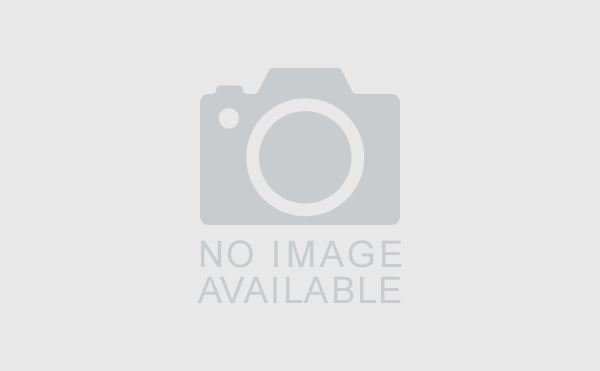あるピアノ奏法①知られざる奏法の気付き
①知られざる奏法の気付き
奏法論争は、今に始まったものではなく
1800年代すでにヨーロッパであった出来事。
もし現代のようにSNSのある状況下だったら、
どんな展開になっていたであろうか...
奏法理論に対して世論が色々物申すことは、
昔も今と同じく普通にあったようだ。
イギリスに留学すれば、マティの存在は大きくあるのだろうと想像するし、
ワルシャワでは、意外にも
チェルニー系レシェティツキからのパデレフスキへの流れが強くあって
それぞれ偉人の記録は、各国に伝わっている。
すっかり遅れていた日本でも、井口氏の与えた影響が大きいように
その国の風土による趣向というものは、
どうしても音楽の中に滲み出た特徴となる。
日本は島国であるだけに、
クラシック音楽が輸入されたものであったことは拭えず
大きな流れというものに逆らうこともなく、
多角的に考える、、には、至らなかったのだろう。
日本を背負って留学した久野久氏は、ウィーンでザウアーから言われた言葉に、
自分の弾き方の将来性への落胆からなのか、飛び降り生涯を閉じたが、
師の影は踏まず、特にしきたりというものを大切にする感覚も強く、
また普通に“きもの″を着ていた時代の日本女性という身分もあったゆえ、
そうすることでしか、表す手立てが無かったのかもしれない。
寄らば大樹の陰。でもそこから出て、陽を浴びれば
奏法など様々あることに気が付きたくなくても気付かされる。
それがヨーロッパだったのだろう。
大樹の陰も無い私でさえ、
ワルシャワに行っただけで日本との差異は、現実的に感じさせられた。
もどかしく感じ、また補えない感覚(指先の細かさの必要性)は
やがて隣国ドイツを志すことに繋がったが、
続く宙ぶらりんな暗中模索は、
一旦ショパンから大きく外れるのかと不安にも陥った。
シュトゥットガルトから、打って変わった環境のデュッセルドルフへの経路は、
辛抱しかなかったが、
奏法ゼロからの再生だったゆえ、まだ保ち続けられたのかもしれない。
常に自分の身体とピアノとの連関を考える癖は付いたが
帰国後は、奏法としての師とは出会えず、一人で時間を費やし、
ショパンが愛した音色は、どんなものだったのか
音の質だけを焦点に、打鍵を考え続けたりもした。
なんのしがらみも無い自由な私の追求進度は、行きつ戻りつしたが、
やがてその鈍間の中で、自分の身体に不思議な感触が宿っていることに気付いた。
それはデッペ理論に基づいた奏法に近似し、
その起源がドイツで、歴史的背景に小さな論争があったことを知ることにもなった。
デッペの探求から導き出されたピアノを弾くために必要な運動神経の意識。
彼の生存時、その奏法は確実に生きていた。
当時のピアノ奏者たちの手の障害に向き合ったことから生まれた彼の論説は、
年号は古いけれど、根拠のない安易なイメージ奏法ではない。
産業革命の影響を背景にショパンの奏法は、「やがて消えていくだろう」と言われた。
理由を同じくしてデッペの奏法も同じ匂いがあったのは否めない。
だが、人間の身体は、その頃から変わっていないのだ。
その頃のような歴史的背景が無い今。彼が論じた根拠が今にも通じる可能性を、
全否定することはできないのではないか、と私は考えている。
②故障に向き合ったピアノ教師 へ続く..