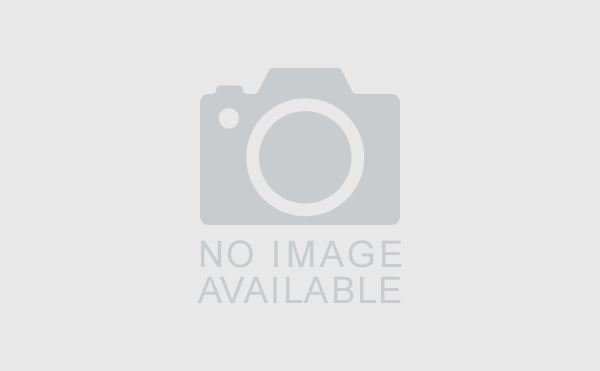デッペと抗力 ①羽根の気付き(前編)
デッペと抗力 ①羽根の気付き
ネットを介せば、情報がワンサカ手に入る昨今。
に対し、
インターネットの普及が無く、まだ電話回線を使っていたような昭和の頃は、
書籍や音楽雑誌が多数出版され、
華やかだったろう音大の多数の生徒も
情報源としてそれを手に取って学んでいたのだろう。
日本のピアノブームは、ヨーロッパから100年遅れて来た。
奏法ブームもそれと同じくしてか、
2000年頃の音楽冊子を見ると、著名な先生方が各々の奏法について自論を寄せ、
連載シリーズになっているものもあったようだ。
検索からピックアップし、それらを取り寄せて読んでみると、
故原田先生の存在に必然的に面することになり、
同時に、酒井直隆先生の著作・翻訳に触れることとなっていき、、、
デッペを知るきっかけに繋がっていったと振り返る。
「デッペの奏法理論 邦訳/原田吉雄」 (絶版)ののちに
手の専門医として酒井先生が書かれた書籍を手にすることとなったが、
後者は、本来、手の故障がきっかけで読まれる人が多いかもしれない。
おそらく酒井先生以上にデッペに関して書かれている日本の書籍は、
存在しないのではないだろうか。
他にも、影響を受けて書いたという序文のあるもの(絶版)もあるが、
そこまで深堀りされていないように見受けられる。
昭和の学生ならば、必ず知っている春秋社版。
その重鎮であった井口基成氏が、
昭和28年(1953年)、
フランス留学を終え帰国してから、かなり後の執筆によるものと思われるある古書。
そこには、
『デッペはドイツの優秀なピアノ教師であるが、
奏法として○○○○だけのものであり、<中略> ○○○○にすぎない』
とあるが、
これはおそらく日本人著名音楽家によって、
デッペに関して書かれた初めての紹介文らしい。
2000年になってからの酒井先生、半世紀以上前の井口氏のどちらの書籍も、
デッペを特別とりあげているのではなく、
ヨーロッパにおける奏法の歴史の流れの多くの中の一人として説明されているが、
出版された書籍としてデッペに関した文字を残している人は、
この3人の先生方であろう。
学生を含めた日本の論文に、デッペに関して触れているものもあるが、
酒井先生や原田先生の著作を数行引用し、
デッペの延長線上にブライトハウプトがある、とする内容がほぼであり、
両者が別説であるとしているものは、無さそうである。
博士課程の研究論文においても同じくで、
何十年も前の分析からあまり変化していないことは、正直、歯痒い。
研究材料となる新しい文献や古書は、
貸出はできなくても国立図書館に蔵書としてあるようだが、
学生が学生の論文に頼ると、同じことの繰り返しになるのだろう。
翻訳本は、大概著者でない他人様によるものなので、
解釈違いによる誤訳をゼロにするというのは、なかなか難しいと想像する。が、
原書をさておいてしまうと、結局この繰り返しになり、真実が遠のくのだろう、
と感じる。
酒井先生は、おそらく
医学博士としてだけでなくピアノ奏者としての見識も持っておられ
ご自身は、また別の弾き方をされているのではないだろうか。
デッペを肯定も否定もせず、医者として公平な立場をとられ
ヨーロッパの奏法歴史についても、
近代の情報まで非常に分かりやすくまとめられた方。
まだこの本を持っておられる諸先輩方も沢山いらっしゃるのでは、と想像する。
だが、文中で引用している外国書をご自分で訳されている部分に関しては、
私の自分訳と異なる箇所が多々あり、
根底に認識の違いがあるかもしれないのが伺えることは、
リスペクトの上で、正直に記しておきたいと思う。
原田先生の本は、邦訳を託された翻訳本であるからして自論ではないけれど
あとがきにご自身の寄せ書きもされている。
たしかご自身は(私の記憶違いかもしれないが)
ランゲンハーンの流派をドイツで勉強されていたのではないか、と記憶している。
デッペと抗力 ①羽根の気付き(中編)へ続く