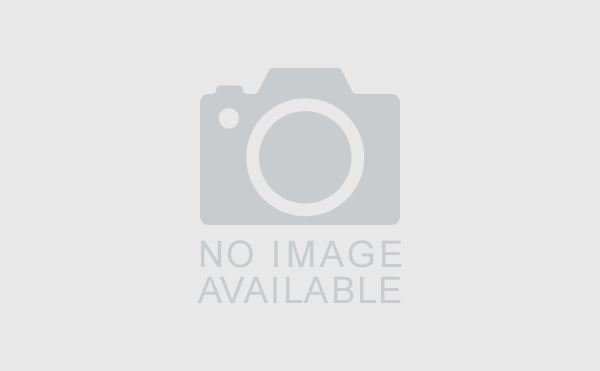調律とレットオフ
先日、ようやくピアノの調律・調整をお願いできた。
ほんの僅かだったのだが、鍵盤の中に動きの違和感が拭えない箇所が
3カ所ほどあったので、そこも伝えて作業をして頂いた。
ピアノに少し触れただけで、
普段、弾き手がどんな風にハンマーを操っているのかが、
すぐに分かる調律師さん。
作業が一通り終わったあと、
「最近、鍵盤へのアプローチ面で何か変えたことありましたか?」と尋ねられ、
先月自主開催した、古楽器と現代楽器の自主コンサートの話題になり、
自然と、楽器そのものの歴史やアクション機構に話が及んだ。
ショパンが愛した“シングル・エスケープメント”と、
現代ピアノに採用されている“ダブル・エスケープメント・アクション”との
違いについても拡がり、
短い時間だったが、とても興味深いお話ができた。
なぜショパンはシングルを好んだのか。
それは現代ピアノにおいても、メーカーごとに異なる個性に
どこか通じているのではないか—
そんな視点から、調律師さんの語るアクション機構の話はとても面白かった。
今、私が使っているピアノはまだ新しく、一人使用でもあることからも、
今のところレットオフの感触状態が良いままキープされている。
私は、この レットオフ を探ることが好物で、
メーカーごとに異なるその深さや感触、その楽器ごとの個性の現れが
面白いと感じている。
レットオフが始まる距離は、
深さおよそ7ミリ、底に達する手前の約3ミリ…などという文面を見かけたりするが、
もちろん、これは正確な数字を指す意味ではなく、楽器によっても違うゆえ
あくまでイメージとして捉えた方がベターであろうし
実際スタインウェイなどは、もう少し浅めという声が多い。
いつもより深く感じるものでも、バランスが取れれば、それが不快なものでなく
心地よい深さに変わる感触が存在することが愉快に考える。
レットオフまでの数ミリは、音が生まれる手前の、貴重な「抵抗点」。
雑なタッチで押し切れば、不要な雑音が混ざるかもしれない。
でも、音になる直前のその“静間”は、まるでまばたきのように儚く、
そして何かの物語が始まるような瞬間でもある。
レットオフは、いつも私に問いかけてくる。
――その時こそ、音の入口に立っているのだ。