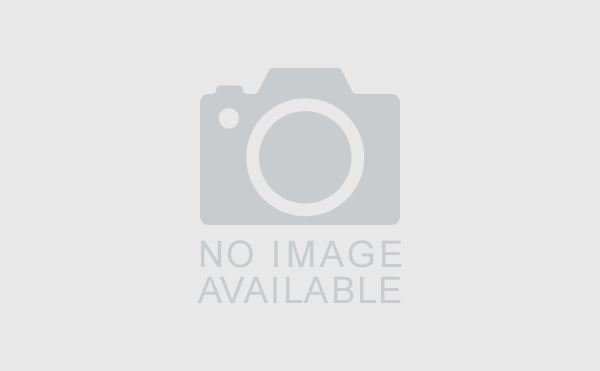デッペと抗力 ①羽根の気付き(後編)
①羽根の気付き(中編)の続き (一部、以前投稿と重複あり)
ショパンに関しても、彼の死後、
奏法の草稿を、姉のルドヴィカが書き留めたという話があるが、
同じような流れが、デッペの身の上にも起こり、
死後、愛弟子カラントが代筆するという形になった。
レシェティツキの奏法本を弟子のマルウィーヌ・ブレーが書いたのが
少し似ているが、まだ生前の元気な師がそれを手に取って読み確認し、
認可済み太鼓判をもらった上、コメントも添付された出版物である点では
状況は大きく異なる。
そんな事例もあるからか、実際
カラントが記したデッぺ論の証明性はどうなのか、と唱える異論もあるが
これは、弟子たちによる著作の内容に、正直バラつきが見られる所以もあるだろう。
それぞれ身体の内面で認識した感覚を踏まえて書いていることは
嘘ではないはず。だが
デッペ論の羽根を理解したという早合点の末であれば、
内容が一致しなくなっていくのも当然だろう。
それがまだまだ先のある早合点のものであったり、
はたまた勘違いの幻のものである、と自分で気付くことの方が、
むしろ難易度が高い。
自分の存命時に出版された弟子の本を見て、
デッペは、どう感じたのだろうか。
草稿を託したカラントには、意志の伝えられるうちから
別の期待を託していたのではないか、と感じる。
デッペの教えは、彼の死後もカラントによって更にアップデートされ、
著作には、生理的な見解も加わった図、写真も介して詳細に説明された。
カラントのコアを理解することでデッペの美学の本質がはっきり見えてくる。
レイモンド博士の助言を受け、
作成したであろう筋肉の図解とカラント自身の骨のレントゲン写真などが
貼付された版はレントゲンの発明(1895年)が証明するように、
1900年以降の出版である。
彼女の文章は、どの文献も読み辛さを感じるのは否めないが
ややもすると誤解や曲解が付きまとうその価値と美学は、
カラントによって一貫性をもって解説し続けられた。
筋肉の構造は、男女の差異あれど基本誰も同じ。
デッペ=カラントの考え方は、
その上で筋肉と物体間の力の伝導が強調されている。
静止体の中で働くピアノ、ピアノを弾く身体。
高貴で軽く、美しい音にこだわったアプローチ。
ピアノを弾く身体をどう認識すべきかを、
デッペスタイルとして遥か150年以上前に唱えていたという時系列は、
エルギン・ロス氏も述べるように、今にも繋がっている。
デッペと抗力② へ続く…