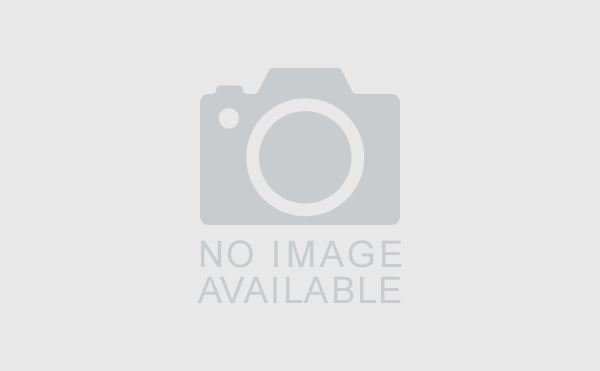シンプルの再発見
お初の試みだった25日のトーク主体ミニコンサートは、
身内の方に来て頂けて、なんとか無事終えることができた。
お粗末な構成のトークを実験のように広げていたにも関わらず
終始真剣に聴いて頂いて、とても助けられた。
ほぼ無名な人物について、
生まれおちから弟子との関係性まで1時間にまとめるのは難しく、
質問が出れば、時間はさらに必要になる
ただでさえ理路整然と話すことに慣れていない私の脳みそは、全開に。
そのあとの演奏とは、別置きの体力がいることを実感。
その配分を計算して臨まないと
デッペの汚名返上トークの後の演奏のころには、色々働かずじまいになる、
という自分を知った。
「慣れ」という技術でも、これはコントロールできていくものなのだろうか。
肝心の音にできなければ、結局、最終的オチに至らないことになってしまいかねない。
そんなことを実践から痛感。
お客さんの人数が少なければ、資料を回しながらのトークも可能だが、
多くなってはそれもなかなか難しいことになる。
「言葉こそ誤解の源泉である」という後世の言葉を、
己がまた繰り返してしまっては、まったく無意味なことだ。
デッペの時代と同じく、
「それは羽根のようにかるく、、、」という告知は、
世間の気に留まらず、不信なものになることは、現代も変わらない。
「いくらでも弾くことができる、鍵盤をねじ伏せる強靭な指にするには?」
「鍵盤をしっかり弾くにはどうしたらいいのか?」
と、打鍵の捉え方、根本的な主観が違い、聞く耳も閉ざされていれば
まったくリンクしなくなってしまうだろう。
手や腕の重みをかけるという重力奏法からすれば、
「軽い手」という文字は、想像外。
力学的にも大きな力を生む可能性が見えない理論となり、その分野からは問題外になる。
ヤンケ奏法論であるヤンケ先生は、デッペ論は不可能とされているようだが、
大勢の手の故障に対処した事実と当時の弟子たちの動きを考慮すると、
デッペの頭脳は一般的な想像の域には居らず、浅い理論を確立させていたわけでないと思わざるを得ない。
結局「脱力」を考慮せざるを得ず、常に付いてまわる奏法である限り、
ハイフィンガ―が廃っても、固定観念と先入観が浸透し蔓延っているこの現代においては
手の故障は、なかなか無くならない気がする。
重力は遠心力を含め、地球上逃れることのできない物理現象、
誰でも同条件に受ける影響
容易に動かせない物体の中に存在する、梃子の動きを操作するということは、
雰囲気でもファンタジーでもない。それを理論的に捉える身体の生理学
何が必要なのかは、蓋を開ければ
人の感情で変化しない、複雑の中に隠れた一定のシンプルなもの。
鍵盤を前にした己をいかに自由にできるか。だ。