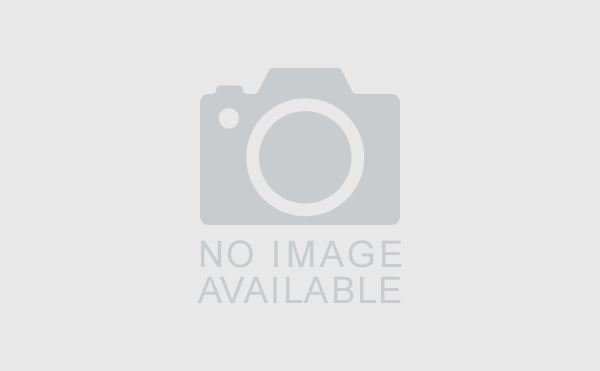ショパンのストリートピアノ
そこに偶然居合わせた人のためのストリートピアノ
世界のストリートピアノの始まりを調べてみると、
2007年か2008年
イギリス人のルークジェラムが『 私に触れて、私を弾いて 』というキャッチコピーで
始まったものとされているようだけれど
今回の話は、
「ショパンのすべて」という記事を書いていらっしゃる方が書かれている内容であり
ショパン好きの間では知られているエピソード。
時は1828年10月6日だと思われ。
あのショパンが、出発前に狂喜乱舞したベルリン旅行の帰り道でのできごと。
これは1888年、フリードリッヒ・二―クス(1845年デュッセルドルフ生まれ/1924年エジンバラ没)という
ショパン研究家が書いた、書籍の中にも出てくる一説。
彼は、書籍「弟子からみたショパン」の中にも、よく目にする名前の人である。
ベルリンからいくつかの場所を立ち寄りして、フランクフルトを経て
ドイツ/ポーランド国境の町、チューリハウという町で、
馬車の用意のため一時間ほどの待ち時間にあったお話
きっとそこからポズナン経由でワルシャワへ戻る経路での一場面だったのだろう。
興味深いことに、ショパンは駅舎に置いてあるピアノを見付け、自ら弾き、
居合わせた周りの人達は、
おそらく弾き手の将来が無限であったことなど知らず演奏に聴き入り、
駅長さんからの「続けて弾いて!」という言葉で、さらに即興演奏をしたという。
この時、披露した曲はポーランド歌曲だったそうな。
二―クスは、あの本に書いてある通り、年齢から言っても専攻楽器からしても
ショパンの弟子ではないので
これは、ベルリン旅行にショパンが同行をさせてもらった教授の言い伝えか、
もしくは誰かからのそれとしての内容であるだろう。
ちゃんとした建物ではなく、駅舎ということなので、
言うなれば „ ストピ ” っていうやつ。
想像すると、これが海外発祥の元祖ストリートピアノのように感じる。
ふとそこにあったピアノで
たまたま時間を共有する、居合わせた人を和ませたショパンの気持ちに
自己顕示欲は全くなかっただろうと感じる。
なぜ弾いたの?と尋ねたら
「散歩も飽きちゃったから、そこにピアノがあったから」 なんて答えそうだ。
穏やかな気持ちで奏でている人も見られるけれど、
日本の騒音に打ち勝つべくフォルテの狂騒で弾かれるのが
どうしても目立ちがちになる現在のジャパン・ストピは、
自分の音に非常に敏感だっただろうショパンにとって、想像外だろう。
『どうせ僕のワルツを、みんなこんな風に弾くんでしょ、、』と、
皮肉って彼の中にはありえない演奏を真似てみせたショパン。
良いとこどりの部分切りばりの演奏も、自分の曲を意図しない音楽で表現されるのを嫌った
ショパンが望むことだったとは、思いにくい。
リストも、そこにピアノと貴婦人が居れば弾いていただろう。
現に、ウイーンから噂の名うてが現れたと聞いたリストは、
タイマンのためにパリに戻り、人々に評価を仰いだ、という話があるくらいゆえ。
独奏性の強いピアノと言う楽器は、その人の生き方で利他的にもなり、利己的にもなるが、
どうしても私はそこに神経が行ってしまうのは、つくづく損な性格だ。
200年前の若きショパンのドイツ旅の終わりの一場面。
そこにあったピアノに触れた時間は
周りの人と癒しを共有するひととき、という本来のストリートピアノの意味を
反利己的なショパンが表しているように感じる。