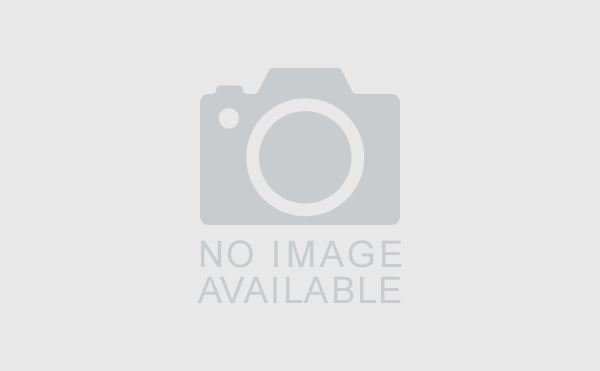パガニーニからの贈り物
ショパンは、ドイツ旅行の翌年、
ワルシャワで5月から7月の間に11回行われたパガニーニのコンサートの大半を
聴いたと記されている。
影響されたのは、特定の人だけではなかったのだろう…
当時ワルシャワの町では、パガニーニスタイルという装いが流行ったという
記録があるのだけれど
あの肖像画に似たような服装の人が、ワルシャワの町を闊歩したということなんだろうか…
フレデリックは、大学の学長さんから
我が音楽院のショパン君だと紹介され、パガニーニの右手と握手を交わしている。
ヴァイオリンのヴィルトォーゾと言われたパガニーニの右手から、
ショパンの右手は、何を察したのか。
リストは分かりやすいそのイメージそのままに
超絶技巧曲で自分の天才ぶりを揺るがないものとしたが、
ショパンが残した「パガニーニの思い出」は、一般的にはあまり知られておらず、
ショパンの作品に多々ある亡くなってからの出版にあたるもの、
つまり番号のない存在のものになる。
研究家の二―クスは、この曲の存在を知らなかったと書いている。
ニークスは「残念なことにショパンがパガニーニの感想について残していない」と
著書に書いているが、デッペの弟子カラントの古い書籍には、
パガニーニの1ボーイング内の音の集約についてショパンが感銘を受けていたという
エピソードの引用がある。
特徴的だったパガニーニの立ち姿勢、構えからくる身体のシルエットは、
当時としての通例から逸脱した惨めなスタイルとも言われたようだけれど、
そのヴィルトォーゾ的な音は、
そのスタイルからこそ生まれているものであり、否定できるものではなかった。
ショパンは、
パガニーニの何に興味を持って何回も演奏会に足を運んだのであろうか。
握手をした右手の感触、そしてショパンが見た舞台上のパガニーニの立ち姿勢と
そのボーイングの音から、何を読み取ったのだろうか。
一音でさえ、拘りうるさかったショパンが、
発音に興味を持たないはずはないと考えさせられる。
若かったショパンは、その出会いから数年のうちに、
めざましく成長を遂げた。
ワルシャワを離れ、ウイーンを経たパリで、
憧れだったカルクブレンナーの弟子入りへの招待を断ったのは、
ショパン自身の奏法の確立されたものへの自信でもあったのだろう。
そもそもブレンナー氏が開発した、器具に手をはめ込むなんて思考が
ショパンの中にあるはずもなかったが
自分の奏法をさらにというある確固とした理念があったのは、
父親との手紙のやり取りからも感じられる。
ここから何年後になるのかは分からないけれど、
ペルッズイ夫人という人が
アウグスト・レオ夫妻(モシュレス婦人のおじ?)の家にパガニーニを連れ立ち
ショパンの演奏を聴かせている。
このパガニ―二エピソードは、二―クスの著書に出てくるが、
ショパンが夫妻と親しく付き合い、好んで通った音楽サロンであり、
モシュレスとの連弾もここだったようだ。
この音楽サロンの存在は、「弟子から見たショパン」でも紹介されている
ショパンが友とする音楽家と共演を楽しんだ、お気に入りの場所だったようである。
ショパンと連弾をして自分が足を引っ張ったかのようなリストの発言があったのは
ここでの演奏のことなのだろうか、、、、
ここでの連弾をきっかけに、モシュレスは、ショパンに娘の師事をと思ったのか、、、
この音楽サロンで、パガニーニはショパンの音を聴き、魅せられ、
ふたりは互いに非常によく理解し合ったようだ。
ワルシャワでのパガニーニとの出会いから時が経ち、
ショパンにとっては、さぞよい年月の頃だっただろう…