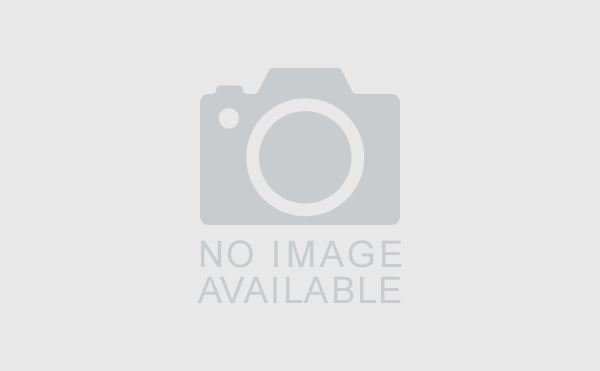ありのままのピアノアクション
今のピアノになってから、もうかれこれ3年以上が経った。
買い替えまでのそれ以前、4、5年の間、悩みに悩んでいたのだが、
その根幹は、その時のピアノの調整がどうしても揃わないことだった。
調律ではなく時間をかけて調整を施してもらっても直り切らない代物、
当メーカーのエリアトップに入る調律師さんが触ってもお手上げになる難物。
極端でシンプルに表現すれば、鍵盤の自重がバッラバラだった。
正直、それなりに贅沢な機種だったのは否めないのだが、
(それは経年劣化による症状ではなく)
もともと持っていた個体の個性のようなものとして受け止めるしかなく、
調律師さんも、状況的に、それ以上やりようがない、
こちらが諦めるしかない判断に陥っていた。
鍵盤のバラバラ感を、気にせずにいける奏者の方もいらっしゃるだろうが
その時の私にとっては、それが大きなネックで、一番の要なものであり、
皮肉にもそれが別の出会いのきっかけを作ることとなった。
ピアノメーカーのチョイスに苦慮していた私は、
誰というのでなく調律師さんが世に出されている記事を読み漁った。
実際、楽器店やピアノ販売店、中古販売店にも足を運び、
試弾をさせてもらっては、文字情報と現実の感覚とのすり合わせを重ねた。
その先、あるピアノ調律&販売会社の社長さんに、
ピアノアクションのことについて感じる自分の悩みを直接話す縁が訪れた。
同時に、調律に関するあんなこんなや、ピアノ業界の諸事情など
本当に様々なお話を社長さんから聞かせて頂いた。
一度はすべてのこだわりを捨て、
自己欲求の7合目くらいで納得するしかないのかとも思い始めてもいたのだけれど
お話を伺い、知ったことで、
ローカル活動人としてピアノに携わる自分を分かっていても
逆にアクションに対する拘りが譲れなくなる現実から抜け出せなくなってしまった。
それからもあちらこちらに試弾に行き、様々なメーカーや年代の感覚も確かめたが
中古含めてどうにもこうにも、確かなものに辿り着くことがなく、、、
その中、地元エリアでは触れる機会をどうしても得れないメーカーがあった。
知らない、全く触れたことがないというのは、どうしても心に引っかかり続ける。
まずは触ってみなければ分からない、そこから冷静に考えようと
当時、そのメーカーのショールームにサイズが揃っていない事は承知だったが、
足を運ぶことにした。
結局、一度で済まず、再度訪れることとなり、
二度目は、自分がそれまで使っていた長さに近いサイズの
入荷に合わせての日程となった。
グランドピアノは
一定の大きさから感触が明らかに変わる(感触を感じる:個人的感想)
実のところ私の前に一人先約があったらしいのだが、
その人が権利を放棄し、私に試弾の順番が回ってきた。
初めて打鍵したそれは、自分の求めていた厳格なアクションだった。
なぜ前の人がこれを放棄したのか、信じがたい。。。と疑問が広がったが、
理由は全く別のところにあったのではないかと今は思っている。
しかし私にとっては万歳三唱、の降りてきた運だった。
そのアクションは
確かに試弾前に完璧な調整もして下さっていたのだろうが、
鍵盤の動きと同時に「これは…(違う)」と騒ぎたくなる驚きにも近く、
それまでのものとは明らかに違うことが手に取るように分かった。
つまり、一番奥にあったフルコンと何が劣るのか、劣らないと思わせる感触だった。
それには、当然の理由があった。
のちに自宅に当ピアノが来て、
専属の調律師さんが調律にみえた際に初めて聞いて知ったことだったが
そのピアノは、メーカー社長が未来を見据えて
通常備わるアクションではなく、
本来とは異なるアクションをあえて入れたオリジナルだったのだそう。
自分が受けた印象と感覚はあながち間違っていたわけではなく、
事前情報や固定観念によって脳がバグって誘導されたものでもなかった。
つまり、販売店のオーナーは、ピアノと音楽に誠実で
私の気持ちを営利目的で誘導するような文言を、一切情報として話さなかったのである。
これがピアノが手造りで、
その時の事情、こだわりをもって製作されるものの運命。
弾きやすいものが欲しかったわけではなく、ただ音が良いものを求めていたわけでもなく
自分のアプロ―チに忠実に敏感に反応する、己に厳しいアクションが必要と
その時の私は思っていた。それで修練すべきだと。
例えば、「コントロールしやすい」という言葉は、私には疑わしく、
そのままよいしょせずピアノが現実を正直に言ってくれるからこそ、
研鑽になると考えていた。
フルコンと肩を並べるタッチ(反応)
それは指を1本すっと下ろしただけで感じ得るもの。
良い楽器は自分のできないことを制覇するためのカードを差し出し
その探究にシビアに応えてくれる。
日本には、いまだ伴奏を浅く捉える風習があるようで
音が出やすくなっている古い日本のピアノの場合、
音が出ちゃうなら屋根を閉めればいい、ソフトペダルを踏めばいいと
未だ考えられがちだけれど、それでは根本的対処にはならない。
伴奏時、ソロとはまた別のコントロールを要するわけだが
その技術も、ただ弾きやすいだけでは学びにくい。
良いピアノという概念もひとそれぞれにあり、、、
と感じる今日この頃である。