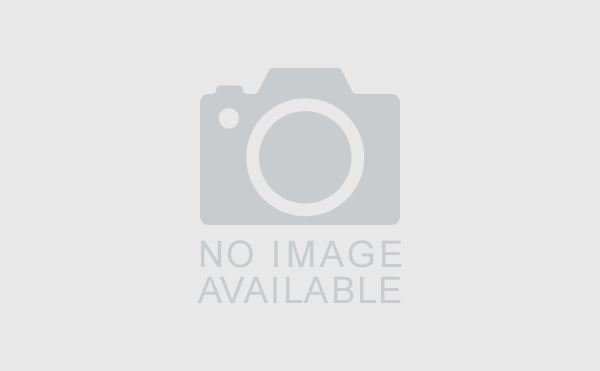あるピアノ奏法② 故障に向き合ったピアノ教師(前編)
デッペとブラームスは、
作曲家のエドアルド・マルクスセンのもとで同時期に学んだ弟子同志である。
その後、デッペがベルリンの地で芸術家として活躍する中、
ピアノ指導者でもあった彼のもとを多くの腕の故障者が訪ね、
ピアノ奏者たちの現状と向き合うこととなった。
その中、
悩むピアノ奏者たちを救いたいという使命感とともに
ピアノ奏法史の先駆けとなる理論を確立していった。
とは言え、
タウジッヒやクラクの弟子だけでなく、
当時ヨーロッパ中にいたとされる高名リストの弟子たちもが
無名とされる部類に入っていたであろうピアノ教師デッペのもとへ
ドサッと移動したというのは、かなりの逸話であり、
当然、リストは機嫌を損ね、軽い嫉妬になったという話も大変興味深い。
アメリカ出身のデッペの直弟子、エイミー・フェイのドイツ留学日記には、
特に影響を受けた教師の一人としてデッペが記録されている。
エイミー・フェイは、タウジッヒ、クラク、リストの後に
デッペにアプローチし、直弟子となった著名ピアニストだ。
クラクは、練習曲として最近も取り上げられているモシュコフスキーが
所属していた音楽院の創立者で、当時リストとも共演した著名ピアニストだった。
日本ピアニストの久野久が、ウイーンで飛び降り自殺をした要因の一つでは?と
言われている、彼女の奏法に対する厳しい批判を行ったのは、
エミール・フォン・ザウアー。
彼は、リストの高弟とされているけれど
アントン・ルビンシュタイン、そしてデッペにも指導を受けたと記録が残っている。

(Deppeの論文がカラントによって再掲載された新聞の表紙)
デッペは、本来、自書で奏法に関する本を出版することを目途としていたが、
実際叶ったのは、故障したピアニストに関する数枚の論文発表のみだった。
イギリスの医師ポーレが、手の障害に関する症例を1887年の雑誌に投稿したが、
それ以前にデッペは、ドイツの音楽新聞に示唆していたのである。
自分の理論確立の成果として出版を果たすことはできず、
デッペは、62歳でこの世を去ってしまったが、
ここで重要なのが、直弟子だったエリザベス・カラント女史の存在だ。
デッペの奏法に関して、デッペ自身が著作した書籍は、この世には存在しない。
彼女の理解能力にデッペは確かな確信を抱いていたのであろう、
唯一遺稿を託されたカラントは、彼の死後、それを受け継いだ著作を出版し、
やがてヨーロッパの各地で第5版まで重版され、一時的に広まった。
しかし、どの時代も、人には先入観・固定観念がどうしてもあるもので、
時に、不当な解釈、曲解というものが生まれてしまう。
言葉こそ誤解の最大の源泉であることは、変わらない。
皮肉にも、デッペ理論の字面は、
読み手の誤解や本末転倒の勘違いを引き寄せてしまった。
例えば、デッペが「手・のみの重みを使う」と論じていても
「重みを使う」という部分的注視が始まり、やがて「重みを掛ける」と右折し、
そして、羽根のように軽い手と整合性が無いものとして、場外へ。
デッペ生存当時も、
デッペの指導が弟子すべてに浸透するのは容易でなく、それは早合点を生んだ。
結局デッペが遺稿を託せたのは、カラントだけだったのだろう。
その後の彼女自身の何点か存在する遺稿の中には真意を伝えるために、
言葉の選択の難しさがあったことを埋め尽くしたようなものもある。
師を失くし、後ろ盾のなかった彼女の環境は、
ひとときの光明を見るものの、結果としては厳しい現実だった。
同時期のクララ・シューマンの名声を見ると、
カラントが良家の子女であるとか、フィアンセが有名人だとか、
学歴や経歴に光るものがあったら、それも違っていたのだろうか...と
正直思ってしまう。
カラントの住んでいたアパートが位置する現在の建物には、
プレートに名が刻まれ、その証が記されているけれど、
今では、誰も足を止めて見ることは無くなった、
気にすることのない、溶け込んだ一つの光景になっているようだ。
カラントが消えていった背景には、
当時の流行や戦争も大きく影響している。
しかし、私の個人的な感想を言えば、
カラントを知らずして、デッペを理解することはできないと感じている。
(後編に続く)