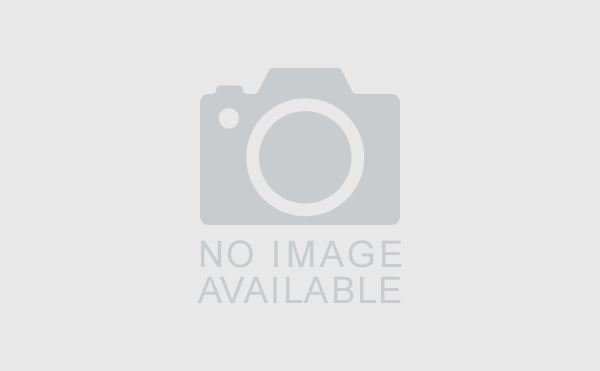あるピアノ奏法③ レントゲン撮影の力を借りて(後編)
<ある奏法③ レントゲン撮影の力を借りて(前編)の続き>
彼女は発表から間もないレントゲン撮影を利用し、
自分の骨のレントゲン写真を論証として、理論の解説を試みた。
(レントゲン発明最初の頃は、専用の場所でなく
普通の部屋に機械を持込、写真を撮っていた?ようである。)
カラントによる首尾一貫の生体理論は、
生理学博士レイモンド教授(生理学的権威の医者家系)の助けを借り、
彼女自身の身体レントゲン写真とともに、
解剖学的な見解に基づいて、次々展開された。
しかし彼女が出版を続けた裏には、
カラントに対抗するかのように出版を続けるブライトハウプトの存在があった。
彼は、「重力奏法」と言えば歴史的文献に必ず出てくる、
元祖のような存在の人である。
実のところ、彼は数か月間だけのカラントの弟子であり、
この事がドイツ以外で、どのくらい知られているのかは分からない。
また一般的には、
ブライトハウプトがその重力奏法の元祖ポジションとして認識されているが、
実のところ、「重力奏法(技法)」と訳せ得る言葉を使用したのは、
トニー・バントマンというデッペの弟子が最初だったようだ。
現実に、師であるデッペが使っていない「重量奏法(技法)」という言葉を用い、
師の死後、独自の書籍を出版した。
カラントは、それをどう見て感じていたのだろうか...
また、ブライトハウプトは、(腕の)重さを用いるというような
一見分かりやすい印象を持つパフォーマンスを謳い、
難解さが無く一般思考に受け入れやすそうな感じが効を奏し、
拡散も自然な流れとなった。
カラントにとっては、ほんの短期間ながらそばに居た弟子ブラウトハウプト。
さっさと自分の元を去り、新理論かのような奏法本の出版にまで漕ぎつけ、
広報活動も上手かった彼の手法はアタリ、
またそれは重力奏法をわかりやすく学びたいというブームを生み、
ブライトハウプトの著作は、売れに売れたようである。
レントゲン写真や解剖図を添付した理解の咀嚼が必要な小難しいカラントの理論は
こうする、ああするというようなすぐに見真似が可能で
実感に繋がるものではなかった故、広く受け入れられることにならず…
外洋に放り出され、波に飲み込まれていく小さな船の主のような
一般的には探されない人の書籍となってしまった。
けれども全く誰も見向きをしなかったというわけではない。
彼女の書籍に、「ブゾーニに捧ぐ」という一節が見開きに出てくるように、
フェリッチョ・ブゾーニが、彼女の理論に同調していた事は
しっかり挟んでおきたい事実である。
抗力とピアノ①羽根のように軽いとは へ続く